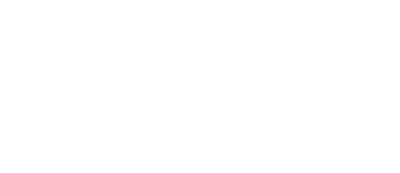台湾の都市を歩けば、数百メートルごとにコンビニエンスストアが目に入る。セブン-イレブン(統一超商)、全家(ファミリーマート)、Hi-Life(萊爾富)は台湾の生活に欠かせない存在であり、単なる食品や日用品の販売だけではなく、公共料金の支払い、EC商品の受け取り、イベントチケット購入など多機能なサービスを提供している。本記事では、それぞれのコンビニチェーンの特徴と違いをまとめる。
セブン-イレブン(7-ELEVEN)

セブン-イレブンは台湾最大のコンビニチェーンであり、店舗数は1万店を超える。最大の特徴は「OPEN POINT」という会員アプリである。飲料購入や公共料金支払いでポイントが貯まり、商品交換や割引に利用できる。
また、セブン独自のカフェブランド「CITY CAFE」は台湾で非常に人気が高く、街中でコーヒーを買う感覚で利用されている。さらに、食品ラインナップも豊富で、日本発の商品や台湾のローカルグルメを手軽に楽しめる弁当やスイーツが揃う。
全家(FamilyMart/全家便利商店)

全家は台湾で2番目のシェアを誇るコンビニである。最大の強みは「My FamiPay」アプリを軸としたデジタルサービスである。スマホ決済との連携やキャンペーン割引が多く、若年層やキャッシュレス利用者に支持されている。
食品分野では「Let’s Café」が有名で、セブンのCITY CAFEに対抗する形で高品質なコーヒーを提供している。さらに、全家はEC受取に強く、台湾のネットショッピング利用者が商品を全家で受け取るケースが非常に多い。
Hi-Life(萊爾富)

Hi-Lifeはセブンや全家に比べれば規模は小さいが、地域密着型のコンビニとして根強い支持を得ている。特に地方都市や住宅街での存在感が強い。
特徴的なのは「Life-ET」というマルチメディア端末であり、公共料金支払い、宅配サービス、コンサートや鉄道のチケット購入まで幅広いサービスが可能である。規模では劣るが、ローカル感を大事にした店舗展開や独自商品で存在感を示している。
まとめ
台湾のコンビニは、単なる買い物の場ではなく、生活インフラとしての役割を担っている。セブンは圧倒的な店舗数とブランド力、全家はデジタルサービスとEC受取、Hi-Lifeは地域密着と多機能端末という強みを持つ。
台湾市場を理解する上で、コンビニは消費者行動の縮図ともいえる存在である。訪台観光客にとっても、台湾生活者にとっても、これらのコンビニは日常と切っても切れない存在なのである。
参考文献
- 統一超商(7-ELEVEN Taiwan)公式サイト
- 全家便利商店(FamilyMart Taiwan)公式サイト
- 萊爾富便利商店(Hi-Life)公式サイト
- 経済日報(聯合報系)「台湾コンビニ市場関連報道」
- 自由時報「台湾小売業ニュース」
- 商業周刊「台湾コンビニ産業特集」
- 台湾便利商店発展協会 資料